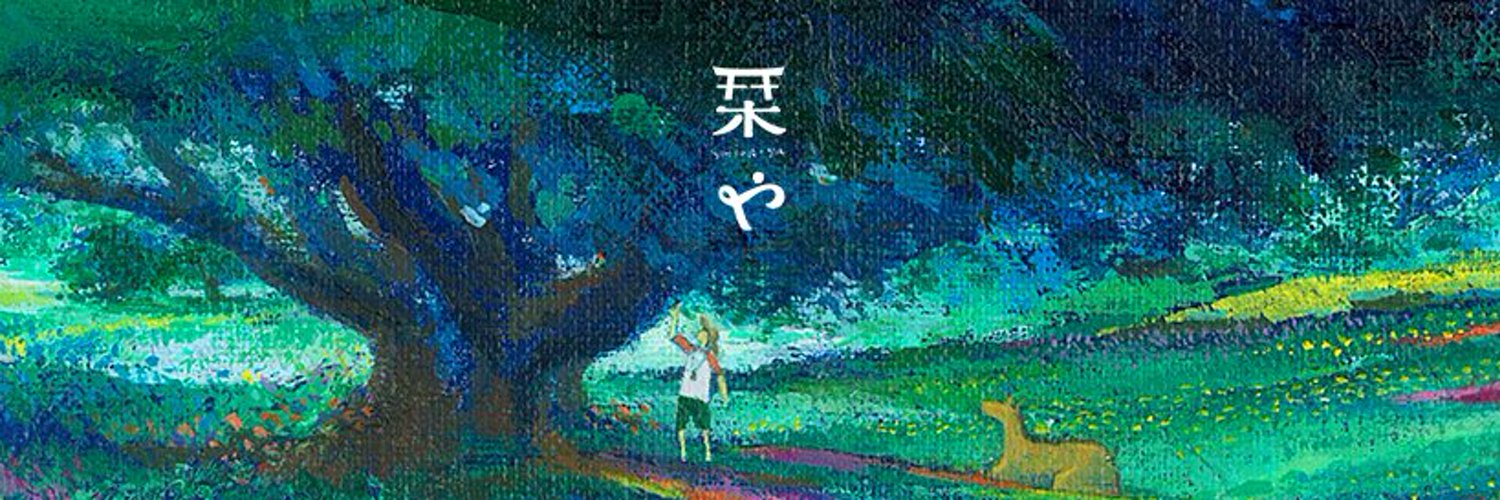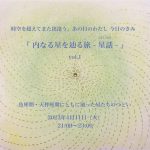“満月には満月の音階を、雨には雨の音階を ”
そんなふうに移ろう自然や宇宙のリズムに寄り添い奏でる インド古典音楽。
「 歌われる季節や時間帯が決まっているんだよ 」
と初めて教えてもらったときの衝撃以来、この世界観、好きすぎる…!
とすっかり心を掴まれてしまって。
どんな世界なんだろうとわたしも知りたくて、体感したくて、
声でのインド古典音楽の学びを 2020年から続けています。
もくじ
一音一音を感じる音の世界で開かれていく扉
今回新しく学んだラーガ『Yaman』は、 “愛のラーガ” 。
このラーガは、インド古典音楽練習生のなかで最初に教わることも多いらしく、また一生かけて学びを深めていくものでもあるという、とっても大事なラーガなのだと教わりました。
過去に教えてもらったラーガにはなかった 半音の “Ma” の音が新しくでてきたり、音階の上り方にはルールの制約があったり。
この音階の上り下りを初めて声に出してみたとき、
慣れない半音をとるのは難しいけれど、ふわふわゆらゆら、独特の曲線の旋律が美しいラーガだなぁと感じました。
( インドでは、ドレミファソラシドを『サレガマパダニサ』といいます。)
たぶんYamanを学ばなかったら自分でこの音階をうたうこと一生なかっただろうなぁ…とおもうので、
Yamanに限らず 初めて学ぶラーガ には、出逢えただけで新しい扉を開いてもらった気持ちになります。
( *** 文章のなかに登場する『ラーガ』ということばは、直訳すると“色彩” とか”心を彩る”という意味です。なので自然観や宇宙観、いろんな感情を表現したり繋がったりするための 特定の旋律 とイメージしてもらえたらいいかなとおもいます。)

「 曲のなかで使える音の種類や、強調したい音、弱い音、音階の上り下りなどのルールの制約があることによって、繋がりたい自然や宇宙観が立ち現れる 」
という考え方をするラーガ。
どれくらいの数があるのかわからないけど、無数のラーガがあるなかで、
『愛』というテーマがあるこのラーガには、この音階だったり、このルールのなかで 音と繋がっていくことにすごく意味がある
っていうことの現れなんだろうな。
練習していくことは、
「いまのわたしなりに、大切に受け継がれてきたこの音をどう感じて繋がっていくか」という試みなんだろうなとおもっています。
音を内側に響かせて、その音が伝えるものと繋がっていくところは、
マントラのチャンティングとも似ていて。楽しい。
マントラも、一音一音に発音の仕方やルールが決められていて、
その音の鳴らし方を学んであたらしい音を響かせるたびに、
ピッとなにかのスイッチが押され、チューニングされていくもの。
よろこび だったり、安らぎだったり、懐かしさだったりを感じたりもします。
決められたその音だからこそ届く。
音は、無意識の場所にさえも、きっと届いていく。
小さな頭で考える “わたし” では届かなかった扉が開かれていく感覚は、
やっぱり音がもつ力なんだろうな。

インド古典音楽のラーガも、ヴェーディックチャンティングのマントラも、
一音一音と向き合うなかで 自然や宇宙のリズム と繋がっていこうとする試み。
いま生きる わたしの感覚や感性と繋げてくれる、神さまの音。
その音がどんなものをもらたすのかは、
どこかに正解の答えがあるわけでもなく、知識でもなく、
その道を自分なりに歩いていくことで
少しずつ開かれていく世界なんだろうとおもう。
だから「一音一音よく聴いて、向き合って」と、めっちゃ言われます。
ラーガとマントラのどちらをやっていても。
そうやって音との向き合い方を教えてもらっています。
ずっとずっと昔から大切に受け継がれてきた音には、
その一音一音に神さまをみてきたひとたちがいる。
こうやって長いときをかけて人から人へと繋がれてきたこの音の世界観が美しくて大好きだし、
わたしなりに歩いてみたいなぁとおもう理由です。
Rāga Yaman での曲づくりに込めた想い
『 いまのわたしにしか唄えないうたをうたう 』ということも
インド古典音楽を学びはじめたときから大事にしていることなので、
今回は、” 愛のラーガ “『 Yaman 』の音階をもとに 曲をつくりました。
『愛』というテーマを感じていまのわたしのなかに浮かんできたのは、
『 音からうまれ、音に還っていく世界 をわたしは愛してるんだなぁ』という想いでした。
抽象的だけれど、愛というものがこの世界を包んで
目に見えないところでずっとずっと昔から、
音とともに巡っている感覚を残したいなとおもいました。
わたしたちが生きる世界には、夜があって、朝がある。
日々の移ろいのなかには 闇もあるし、光もさす。
空を吹く風だったり、寄せては返す波だったり。
長いときをかけて、揺らぎから いのち が生まれ、いまに繋がれている。
「源」とよばれる場所からやってくる 音 や 声。
それらの 響きは 唄となって、祈りとなっている。
そんなぜんぶが 愛となって、この世界を 巡っていること。
ずっとずっと昔から、そして今も。
そんなふうに感じていると、浮かんできたのは『nārāyaṇa』という響きでした。
サンスクリット語の『nārāyaṇa』は、すべての存在の休まる場所・源・水。
音からうまれ、音に還る 神さまの名前です。
自分でつくった曲のなかでは初めて、神さまの名前を唄った曲にもなりました。
音のよろこびを わたしに教え、繋いでくれている
インド古典音楽の先生とマントラの先生への愛を込めて。
日本語 と サンスクリット語のもつ響き、
インドの音階 Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa の音でうたっています。
重ねた音の響きが
愛とよばれる場所に寄り添い、彩るものであれたら嬉しいです。
声・ハルモニウム sanae Kishimoto
感じたことやもしなにか浮かんだことがあれば、コメントやメッセージをおくってもらえたら励みになります。
聴いてくださって、ほんとうにありがとう。
– – – – – – –
▽ バーンスリー奏者・キールタン奏者のgumiさんよりインド古典声楽 ラーガを学んでいます。
https://www.gumi-bansuri.com/
– – – – – – –
▽ 『ヴェーディックチャンティング』というヴェーダの一説を唱えるマントラを、渡部直子さんより学んでいます。
https://www.homeofrainbowspirits.com/
– – – – – – –